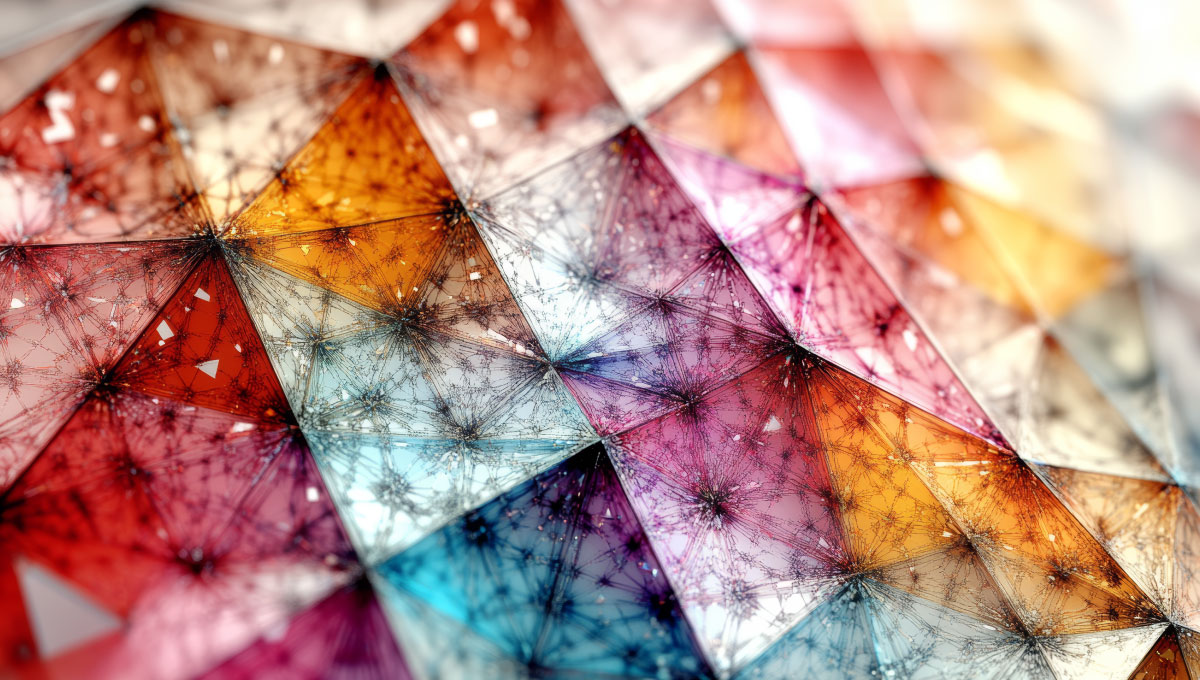INDEX
機械論的な組織原理で運営されてきた組織には疲弊が進む
人間が「自らを修復・進化させていく力」、つまり免疫力を持っているように、生き物としての組織は本来そうした力を内在している。
しかし、機械論的な組織原理で運営されてきた組織は、人間をも部品とみなしているため、成熟期に入ると、この免疫力の機能不全が必然的に顕在化する。
機能不全とは、組織を構成するメンバーの多くが、機械論的な建前で構成された組織原理に支配され続けるなかで、当事者としての姿勢を失い、進化の源泉である「発意する意欲」と「創造性」を失った状態をいう。
社員の発意が今ほど必要とされている時代はない。にもかかわらず、あきらめの姿勢が組織を蔓延し、当事者がいなくなっている今の状態に、危機感を覚える経営者は少なくない。
「自らを修復・進化させていく力」の回復への試みは、至るところで試みられている。しかし、残念なことにその大半は、成功に至っていない。
その主な理由は、回復への多くの試みもまた、そもそも問題の根本原因である機械論的な組織原理、つまり指示・命令を原動力とし、全社一斉というスタンスのままでなされてきたからだ。
回復、再生への試みのため、定量的なモノを対象とする近代の科学的方法論と決別し、あいまいなモノをもその対象とし得る新しい方法論が待ち望まれている。
高度経済成長を達成するための最適手段であった機械論的組織原理
では、なぜ機械論にもとづく組織原理が抱えるこうした重大かつ本質的な問題が、今まで課題として真正面から取り上げられることがなかったのだろうか。
資本主義がまだ成長段階にあった時代は、人間に機械の一部分として機能することを要求することが、最も手っ取り早く経済的豊かさを手にするための道であった。 加えて、当時の日本人は生きていくことで精一杯の状態だったため、そうした要求に順応することがそれほど大きな社会的問題にはならなかった。
その結果、人間を機械の一部として取り換え可能とみなす機械論的な科学的方法論がきわめて有効に機能し、戦後日本の資本主義社会を高度成長に導く時代が長きにわたって続いたのだ。
機械的方法論が戦後日本の資本主義を(当たり前の前提として)支配することになっていったのは、そうした歴史的な背景があったがためである。
(高度成長が始まる時代に唱えられた「期待される人間像」などは、人間を機械のごとく扱おうとした好例である)。
機械論的方法論に代わる新たな方法論の要請
しかし時代は移り変わり、世の中はモノと情報にあふれ、モノと情報の中に身を置く人間も、いつしか多様で高度な欲求を持つことが当たり前になってきた。
今日は、もはや人間を機械の一部として扱うことが、以前よりも簡単ではなくなってきている。
それだけではない。より大きな問題は、21世紀になって、バブル崩壊前とは比較にならないほど、人に発意や創造性が求められる時代が到来している。
もう一つ顕著なのが、機械のごとくふるまうことを強要され続けてきたヒトが集まる組織の劣化である。
機械のごとく扱われ続ければ、ヒトはしだいにその主体性を失っていく。主体性を失ったヒトの集まる組織は、当たり前だが活力を失くし、(本来備えていなくてはならない)自らを変化させ、つくり変えていく自己再生能力を失っていく。
このように変化する環境の中で、人間が持つ、あいまい性を捨象することで成立した近代科学の方法論、今まで何事をも成功に導いてきた近代科学の方法論そのものが、その限界を露呈し、機能しなくなってきているという問題が顕在化してきた。
ヒトの創造性が不可欠な時代、その時代の要請が、今まで世の中を支配してきた機械論的な科学的方法論と相容れなくなってきていることは明らかである。
別の新しい科学的な方法論の確立が急務とされる時代がやってきているということだ。
組織を進化させていくプロセスデザインという方法論とそれに基づく組織原理
科学的方法論にもとづく組織原理であるプロセスデザインは、定量化し難い「人と人との協力関係の質」や「それのもたらす価値」、「協力関係を持とうという人間の意志や意識、感性」などをも科学の対象とする。
それは、物事を可能な限り小さく分割し、対象を静止画像として分析的に扱う機械論的な方法論ではなく、現実に生成する動きの中で対象をとらえ、それを部分であると同時に相互の関係性を含んだ全体(動画)として捉え、扱う方法論である。
「生き物としての組織」が自らの中に、自らを修復・進化させていく力、つまり免疫力のような力を持っているという仮説も、この組織原理の中から導き出されたものである。
そういう意味もあって名づけられたのが「プロセスデザイン」という方法論の名称である。 しかし、この方法論は、まだ完成された方法論とは言えない。
プロセスデザインがその対象とする応用範囲は広いと考えているが、現在のところ、実務的に検証されているのは「人と組織の進化に関連する分野」であり、すなわち組織原理である。
あいまい、ゆらぎを内包するプロセスデザインの方法論(組織原理)
21世紀は、ヒトが持つ創造性の引き出しが何よりも必要とされている時代である。
最大の問題は、従来の方法論である機械論的科学的方法論が、昨今の組織を進化させようという試みや、創造性を必要とする商品開発などの領域でほとんど機能していないことである。
しかし、なぜそのようなことになるのか誰もわかってはいない。そして、多くの企業では、相も変わらず「指示・命令」や「全社一斉」という昭和時代の組織原理が支配している。 組織の進化を機械論的な組織原理で進めようというもくろみは、当たり前だが失敗する。
こうした背景のなかで、その必要性が強く意識されるようになってきたのが(人間が持つ複雑さ、あいまい性、創出力などの側面をも対象に含めた)新しい科学的方法論であり組織原理なのである。
「あいまい性をも対象に含んだ方法論にもとづく組織原理」として提示され、すでに30年近い試行錯誤の中で検証されてきたのが、スコラ・コンサルトのプロセスデザインなのだ。
設計図のない未来を描いていくプロセスデザインに必要な「試行錯誤力」
機械論的な意味での「計画」とは、事前に目標とそれを達成するためのやり方や手順を明らかにし、筋道を立てて予定することである。ここにも、正しいインプットをすれば正しいアウトプットが出る、という機械論的な想定がベースにある。
計画どおりに事を進めようというこのやり方は、現実の状況や条件が途中で変化しても、基本的に変更することを前提にしてはいない。
「計画ありき」の考え方は、設計図にもとづいて建物を建てるときなどには有効に機能する。前例を踏襲するという考え方もそのひとつである。
一方、「プロセスデザイン」は、まだ誰もやったことのない新しい何かをつくるようなときに有効な方法論である。
組織原理としてのプロセスデザインの考え方は、変革の大きな方向性(=めざすもの)を持ちながら、「組織は生命体である」という考えを前提に、事前に計画された手順にもとづくのではなく、試行錯誤の中で当事者の新たな知恵と創造性を引き出しながらめざすものに近づいていく、というものである
したがって、プロセスデザインの考え方にもとづいて物事を進めていくためには、めざすものと、常に変化する現状とのたゆみない対話の中から「今、何が必要なのか」を考え、実行し、修正していく「試行錯誤力」が重要になる。
(本稿は2016年に書かれたものです)