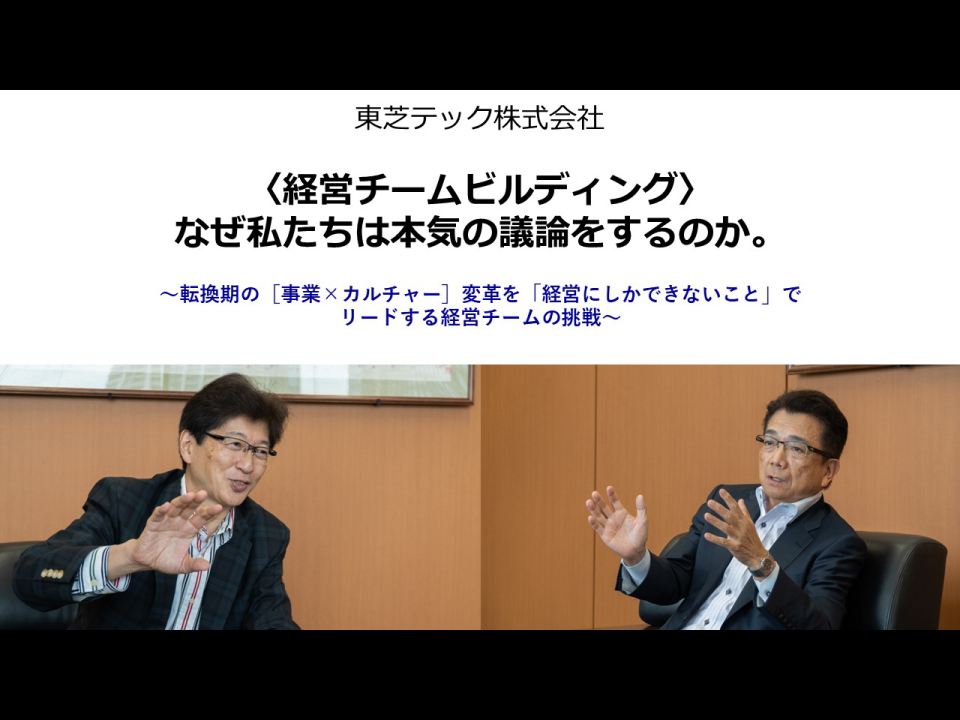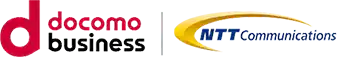「経営と社員のつなぎ役」のジレンマ ~隔たりの大きさに比例する経営の苦労
現場の社員が経営の議論を聞いていると、どんなことにモヤモヤしてくるのだろうか。
「会社の将来をみんなで考えられるような会社にしていこう、みたいな役員の方が言われることは本当にそうだし、そうありたいと思うんです。一方、業務の日常に戻って、日々の実務に追われる人たちと一緒に自分も追われる立場になってみると、少し時間を取って将来のことを考えませんか、とは言えない。その瞬間も操業を止めないように頑張る人たちがいるから会社が回っている。どちらのこともわかるし、必要だし、そこだけ聞くとどちらも間違っていない。でも、そこのギャップ、隔たりが、たぶん役員が思っているよりもはるかに大きいと感じてるんですね」(押田)
会社が変わっていかなきゃいけないことは頭ではわかっている。でも、実際の現場がやっていることとの間には大きな隔たりがある。そこを、どうやってお互いが歩み寄り、一緒にやっていこうというふうにできるか。まず隔たりの大きさを知って、お互いが具体的な次の一歩をどう見つけていくか、ということでしか近づいていけないのではないか。そんな現実的なモヤモヤである。
「自分一人が頑張ってどうにかなるものではないけど、じゃあ、誰かが何とかしてくれるのを待てばいいのかというと、そうじゃないと思っていて」と、押田さんの頭は体を連れて走りそうになっている。
「ミドル層も今、そういう板挟みのジレンマと戦っているように見えますね」とは、三浦さんがずっと気になっていることだ。だから経営には「もっと現場をじかに見てほしいなと思います。実際にリアルを見て、どうしていくべきなのかを真剣に役員同士で話し合って、そして、最後はしっかり決めるというところまでやってほしい」
ジレンマでモヤモヤするのは、社員の二人が現場を代表するのではなく、オフサイトの議論に密着する事務局として、現場と経営、どちらの世界も見えるようになったから。「それが見える状態に置いてもらっている」と押田さん。
見えないからお互いにつながっていけない。それを見ている誰かが間に入って、この先どうやったらみんなで一緒に進んでいけるだろうかと考える。そういう人が必要だと思っている。
二人とも内山さんから事務局としてこういう役割を果たしてほしいとは特に具体的に言われていない。シンプルに「経営と社員のつなぎ役」というだけ。当事者としての姿勢を持つ人は、そこに行けば自分で何かを見つけて考え始めてくれる、と内山さんは思ったのかもしれない。

もちろん、もう一つの明確な意図は、役員の議論に“現場の目”が入ること。その効果は絶大だと内山さんは言う。
「経営の中だけで考えて良かれと思って議論していると、どうしても意見が偏りがちになるんです。それに対して『閉じてるんじゃないですか』と指摘してもらったり、全然違う視点から意見をもらったりして軌道修正している。役員オフサイトに入ってもらうことで、常に方向性、軸がズレないかを確認してもらいながら進めることができているんです。『話、長くないですか』とか『ちゃんとやってください』とか言われちゃうし。だから事務局が何か言ってくれることを期待している役員は多いと思いますね。事務局の人はどう感じているの?とか言ってますから」
役員が事務局をメンバーの一員と考えている。そういう意味では大ヒット、役員オフサイトの成否のカギを握っていると言っても過言ではないと内山さんは言い切る。
そして、現場のメンバーにも「役員たちの本気で取り組む姿勢、考え方をじかに見て何かを感じてもらえたら嬉しい」と思っている。
この事務局に参画して良かったなと思うことについて、「経営がちゃんと話していて、それを間近に見れたことで、会社を良くしていきたいなという気持ちが強くなった、というのはあります」と三浦さん。押田さんは「経営と現場の両方が見えることがありがたい」と感じている。
先行していた改革基盤づくり ~現場層の「対話の場とネットワーク」がこれから生きてくる
内山さんは、三浦さんと押田さんに「経営と社員のつなぎ役」を期待して事務局への参画を頼んだ。どうやって社員と会社をつないでいくか。この思いの背景について内山さんが話してくれた。
「RS事業本部の時にEP推で若手中心の対話会があって、定期的に出て話してみると、若い人たちは本当にいろんなことを考えていてエネルギーもあるんです。自分たちはもっと会社を良くして、やりがいを持って働きたいのにと、彼らは悩んだり悶々としたりしている。でも、それが会社とつながっていないから、その思いや力を生かすことができていなかった」
ヒエラルキー文化の強い会社ではよくあることだが、会社が定期的にやっている対話会でも、社員の意見や要望はいろいろ話してもらうけど、聞くだけ聞いて終わってしまうケースが大半だ。
経営が応えることで、そういう若い人たちが会社とつながって知恵を出しながら楽しく働いてくれるようになれば、会社も社員も、お互いにとっていい循環になるのに…。この思いはずっと内山さんの中で尾を引いていた。
現場が本気で取り組んでいる風土改革活動の多くが、経営とつながらないために徒労や限界を感じて失速していく例は枚挙にいとまがない。それでもEP推の若手社員たちは潰れずに、今も地道に自主活動を続けている。現場が自分たちの動機で考えて動き、対話によって周りを巻き込んでいく活動の持続的なエネルギー。
「こんな例って他社にはないんじゃないかと思います。EP推は当社の大きな強み、改革推進のエンジンともいえる大きな下地です。これが経営と志を一つにしてつながることができれば、これから大きな力になると思っています」(内山)
テックの現場層には、年月をかけて築かれてきた、ヨコの巻き込み力の強い「対話」のネットワーク、変革のソフト基盤が形成されている。自由に発言し、自分たちで考えて動くチームの文化はすでに足元にはある。
この人的資本、関係資本がいよいよ、現場のほうへと手を伸ばす経営によって、活かされるステージに入っていく。