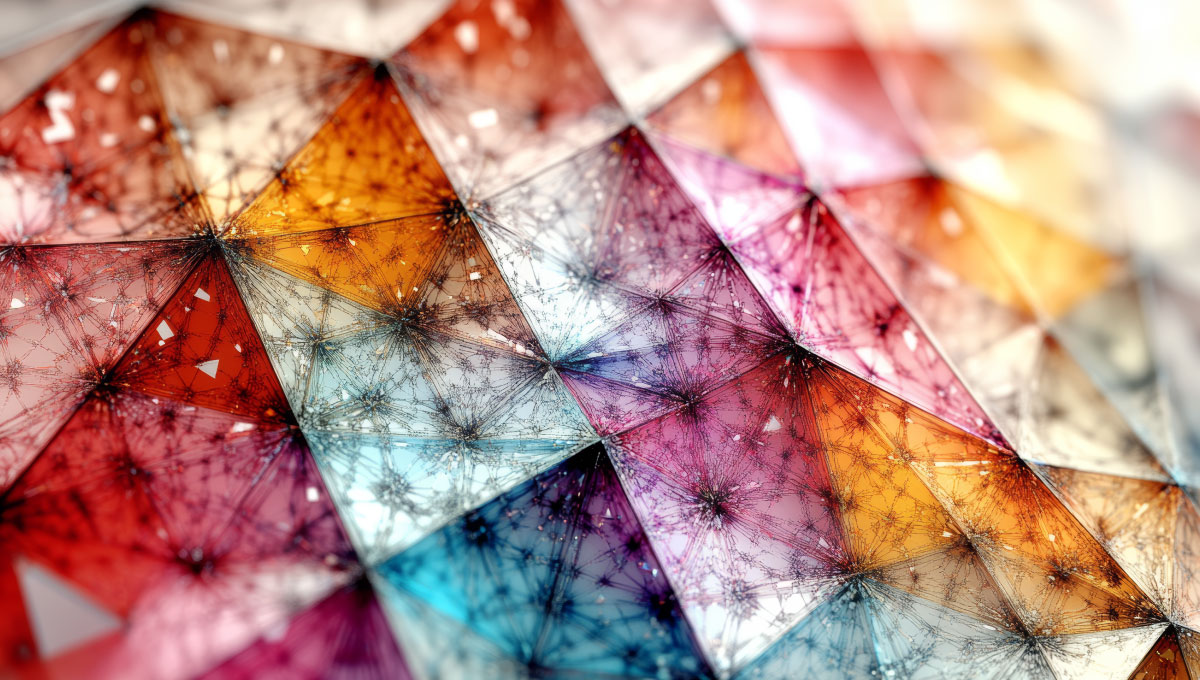前編はこちら
INDEX
オフサイトミーティングが覚醒する ~改革の主役〈拓く場〉としての再定義
見えにくい答えに向き合うことを役割とする〈拓く場〉というのは、私たち日本人にとってはあまりなじみのない場です。子供のころに体験する公教育の場が、決まった答えが用意された〈閉じる場〉という性格が強いものだったこともその理由のひとつでしょう。
「先生が持っているとされている答えに向かって収束させるのが授業」という〈閉じる場〉的なスタイルを、戦後もずっと踏襲してきたのが日本の教育でした。
〈拓く場〉とはそもそも何か。それを明らかにするためにも、対照的な性格を持つ〈閉じる場〉の特性からまず整理しておきます。
〈閉じる場〉というのは、結論が想定の範囲内に置かれていることを前提に仕切られる場です。たとえば、経営から降りてくる課題を納期限にやり切るための業務処理をこなす会議は、こうした前提があることで収まりが良くなるのです。
会議というのは、「発散」と「収束」という二つのプロセスで成り立ちます。ところが、「発散」の議論は〈閉じる場〉にはふさわしくないと考えられています。つまり、〈閉じる場〉はあらかじめ想定されている結論へ粛々と「収束」させていく場だからです。
日本の大企業の会議は、そのほとんどが安定的な現状維持を優先する〈閉じる場〉として運営されている、と言っても過言ではないでしょう。
セレモニーのように仕切られていく日本の会議のあり方に活力不足を感じていた私たちは、1990年頃から取り組み始めた改革の現場で、〈拓く場〉のひとつでもあるオフサイトミーティングを手法として取り入れていきます。これは、“たばこ部屋”に似た「気楽にまじめな雑談をする場」でのコミュニケーションが新たな知恵を生み出すには必要、という今までにない提唱でした。
欧米でオフサイトミーティングと言えば、読んで字のごとく、「場所を離れる」という意味で使われていますが、私たちが重視したのは、場所を離れることだけでなく、「立場を離れる」ことの持つ意味です。そこには、日本の企業では立場に捉われ言うべきことも言えないのが普通である、という私たちの経験に裏付けられた日本ならではの問題意識がありました。
このオフサイトミーティングの広がりは、当時の日本の風土改革の歴史の中でそれなりの意味を持ったできごとであったと思われます。
ただ、その有効性が認められ、急速に広がりを見せた半面、オフサイトミーティングをやってみたら、最初の何回かはうまくいったけどそれ以降が続かない、といった悩みもよく耳にしたのです。
いつの間にか「オフサイトミーティング」という名前だけが一人歩きし始めていました。
今だから言えることは、オフサイトミーティングは、コミュニケーション改善のツールとしては有効に活用されたものの、残念ながら、大企業では改革推進の決め手として「なくてはならないもの」にまで位置づけられることはなかったのです。
結果として、オフサイトミーティングの活動は組織全体の改革における「脇役」に留まり、特に大企業では、部分的な取り組みに終わることが多かったわけです。
そのことが意味するのは、当時はまだ〈閉じる場〉と〈拓く場〉という概念で問題の全体像を捉えられていなかったことです。〈閉じる場〉の裏側に潜む本質を明らかにするまでには認識が至っていなかった、ということです。つまり、日本では儀式のように行なわれる会議が果たしてきた「安定的な現状維持という役割」とその「思考停止の再生産という限界」を、当時の私たちはまだ察知できてはいなかったのです。
今、何が以前と違うのかと言えば、〈拓く場〉という定義が明確になり、改革推進のために「なくてはならないもの」として位置づけられている、というところです。それは、「〈拓く場〉の量と質」そのものが改革全体の成否を左右する最も重要な役割を担っている、つまり「主役」になっているということを意味しているとも言えるのです。
会議を無自覚な〈閉じる場〉にしない「意味・目的・価値」の“問い直し”
日本を現状維持に留めてしまっている悪意のない「思考停止」は、まさに〈閉じる場〉を無自覚に続けていくことで再生産され、常態化しています。ですから、いかにして〈拓く場〉を日常的に体験できるようにするのか、そしてその質を高めていくことができるのか、が勝負です。改革の現場で明らかになってきたのは、新しい価値を創造できるか否かは、まさに〈拓く場〉にかかっているということなのです。
こうしたことを背景に、私たちは実践の場でみなさんに、「今、ここで必要としているのは〈拓く場〉なのか、〈閉じる場〉なのか」という問いをつねに投げかけます。さらに続けて、「みなさんが実際にやっているこの会議の性格はどちらなのか」と問いかけます。
参加者一人ひとりがこの問いに向き合うことで、会議の意味や目的を問い直すのです。
言うまでもなく、何を目的に会議をしているのかでその場に必要な性格は異なります。業務をとりあえず円滑に回すことが求められているだけであれば、〈閉じる場〉的に運営しても特に問題はありません。そうではなく、何か新たな価値を生む必要がある場なら、〈拓く場〉であることが必要なのです。つねにこの違いを正確に認識し、「改革を推進するトリガーは何か」の認識を深めていくことが大切です。
会議では意識をそこに集中していないと、本来は〈拓く場〉の議論を必要としているはずなのに、気づいてみたら、知らないうちに〈閉じる場〉的になっていた、という話は非常によくある話です。
〈閉じる場〉というのは、それほど私たちにとっては無意識に身体が覚えている場だからです。
慣れ親しんだ〈閉じる場〉と、改革の成否のカギを握る〈拓く場〉を分けるもの
〈閉じる場〉と〈拓く場〉では、「何が決定的に違うのか」をきちんと整理しておくことはことの本質を理解するためにもとても重要なことです。
まず、議論の焦点がまったくと言ってもいいほど違います。
〈閉じる場〉では、さまざまな前提が不動のものとして置かれていることが当然で、その前提を問い直すようなことはタブーになっています。ですから、議論の焦点は基本的に「どうやるのか」に終始するのです。業務をただ従来通りに回すにはそれで何とかなるからです。
それに対し、〈拓く場〉では、「置かれているその前提にはそもそもどんな意味があるのか」といった一見めんどうな議論が普通になされます。〈拓く場〉でいちばん大事にされるのは、「何のために」「どういう意味があるのか」などの意味や目的を、折に触れしっかりと議論することだからです。
〈拓く場〉は、〈閉じる場〉とはまったく中身の質が違う、新たな価値が生み出されやすい掘り起こしの場なのです。
簡便な〈閉じる場〉と価値を生み出す〈拓く場〉という二つの場を必要に応じて意識的に使い分けることができるなら、新たな価値を生みだすチャンスは飛躍的に増大します。
具体的な話として、業務上で提携するべきかどうかを検討する、というような新しいことをやるのかどうか、という会議の場面を考えてみます。
〈閉じる場〉では、よく見られる光景ですが、それを実際にやってみたらどういう問題が起こる可能性があるのか、という現実に則した議論が繰り返されます。通常、現状を掘り返せば掘り返すほど、難しさは浮かび上がってくるものです。本来はやる意味のある話であっても、現実の難しさが浮かび上がると「できるか、できないか」の議論になり、「やはり無理だ」という現状維持の慎重論が多くの場合優勢になっていきます。
この会議を〈拓く場〉として運営すればどうなるか。まずは「それをやることにはそもそもどんな意味があり、どんな価値を生むのか」といった議論が徹底的になされます。つまり、現状起点で「できるか、できないか」の議論をするのではなく、「めざすもの」を起点にして議論がスタートするのです。
その意味や価値をしっかり認識した基盤の上に、現実に提携するとしたらどんな問題が生じるのか、といった話になっていくわけです。もし、やることに意味がある、という認識が共有できていれば、少々の困難でもなんとか打開しようというエネルギーが生まれるので、やることを妨げている制約を打ち破る可能性も見えてくるわけです。
〈拓く場〉が「めざすもの起点」の質の高い議論を可能にする
この例のように新しいことを始める場合、〈閉じる場〉と〈拓く場〉という二つの場で対応の仕方はまったく違ったものになっていくことがよくわかります。
私たちは、〈閉じる場〉的な対応を「現状起点の発想」、〈拓く場〉的な対応を「めざすもの起点」と言っています。何かをやり遂げるときには、この「めざすもの起点」の考え方を持っているかどうかが決定的な違いを生むのです。
ただ、「めざすもの」を起点にした質の高い議論をし、意見を戦わせることは簡単ではありません。日頃から考える習性を身につけていない人にはハードルが高い。つまり、自分と向き合い、自分との対話をいつも繰り返しているような考える力を鍛えている人でなければ、中身のある議論はやり切れないのです。
だからこそ私たちは、〈拓く場〉で「そもそも自分の人生にはどんな意味があるのか」といった自分と向き合う議論からスタートすることが人材育成には不可欠だと考えているのです。
まず社内に〈拓く場〉を可能な限り多くつくり、質の高い議論を推進し得る人材の育成に必要な工数をかけることが最初のステップです。そうしてできた仲間と一緒に議論の質をより一層高め、新たな価値を生み出し続ける企業が増えることで、日本に競争力が蘇るのです。
そういう意味でも、この一年が勝負の年だと私は思っています。